
息子は小2から3年間、娘は小1から2年間、「スマイルゼミ」のタブレット通信教育を受講しています。
そういえば、毎日飽きもせず取り組んでるね。自分が子供の頃の通信教育といえば、Z会だったけど、面白味もなくって苦痛だったな~⤵
今のタブレット通信教育は子供が楽しんで学べる仕掛けが一杯だからね!
スマイルゼミとは
スマイルゼミは株式会社ジャストシステムが展開する家庭学習事業です。
「一太郎」とか「ATOK」で有名なジャストシステム?
Microsoftのワードに押されてなくなったのかと思ってた。
そういうことを言わないの。
ジャストシステムは、20年以上も学校教育現場と向き合って、学習ソフトの開発に携わってきたんだって。
そう、ジャストシステムの小学生向けの学習・授業支援ソフト「ジャストスマイル」は、1999年6月の発売以降、先生方や子どもたちの圧倒的な支持を得ているそうで、現在、全国の公立小学校の約8割で活用されているということです。
単に「子どもが使えるソフト」ではなく、現場の先生方と共に開発した教育的な工夫や配慮、子どもへのわかりやすさが好評で、今では「小学校で使う定番ソフト」になっていて、そのノウハウが、スマイルゼミにも活かされているそうです。
だから2017・2018「通信教育」小学生タブレット顧客満足度最優秀賞を受賞していたり、2018「通信教育」小学生総合部門でも、「子どもが好きな通信教育」と「継続しやすい通信教育」部門賞も受賞したそうです。
※イード・アワード2017・2018「通信教育」小学生タブレット顧客満足度最優秀賞受賞、イード・アワード2018「通信教育」小学生総合部門「子どもが好きな通信教育」「継続しやすい通信教育」部門賞

スマイルゼミのメリット
それでは受講していて感じるスマイルゼミのメリットをご紹介します。
1 新学習指導要領に対応
いよいよ2020年春からは学習指導要領が新しくなって、全学年でプログラミングを活用した授業が始まったり、英語は3、4年生で必修化、5、6年生で教科化されます。
教科化されるということは成績がつくということです。
家庭学習でもこれに対応していく必要がありますが、なにぶん私たちの世代ではなかった事柄なので何をどう教えていいかがわかりませんし、先生によって大きく差がつきかねない分野です。
突然、英語やプログラミングを教えなければいけない先生たちも大変だな~。
その点、スマイルゼミはこの新学習指導要領にしっかりと対応しています。
①英語
英語は1年生から標準配信されています。

ネイティブの発音を聞きながら子供が一人で「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく学ぶことができます。
「聞く」 ネイティブの英語を体感できる
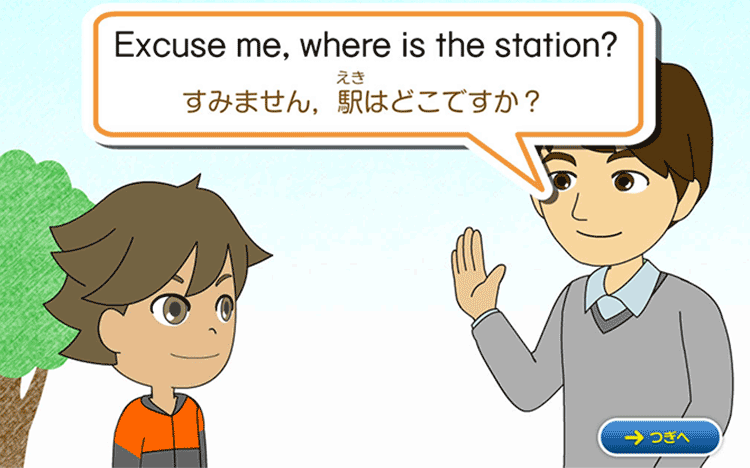
「話す」 自分の発音を録音して視覚的にアクセントを取得できる


「書く」 正しいアルファベットが身につく
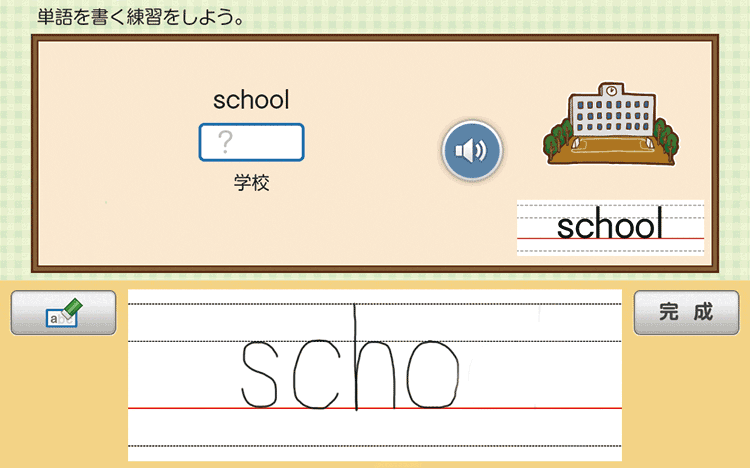
これが全部標準配信で受講料に含まれているのはすごいね。
うちの子たちは受講していないけど、毎月の英語の学習量を増やしたい場合はオプションで「英語プレミアム」も選択できるんだって。

②プログラミング
実はスマイルゼミを申し込む前に、街中のプログラミング講座を見て回ったんですが、月1万円程度と高かったので悩んでいました。そもそも学んだことが学校の授業にどうつながるのかも未知数でしたし。
それもスマイルゼミなら標準配信に入っていて助かっています。
しかも算数・理科・社会という教科と結びついたプログラミングです。


このあたりは、さすが「一太郎」や「ATOK」などのジャストシステムだね。
2 教科書準拠
スマイルゼミは、申し込み時に学校名を入力します。これにより教科書が自動選択されて、学校の授業と同じ内容の学習ができます。

予習・復習にも便利だね。
3 学習専用タブレットならではの仕様
①手をついて書ける唯一の学習専用タブレット
1.7mmのペン先で、細い文字もしっかり書けるので、計算問題の途中式や記述問題も丁寧に書くことができます。

②一人ひとりに“今”最適な学習プログラムを生成
膨大なデータを解析し、子供一人ひとりに最適な講座が生成されるので、学習の偏りがなくなります。
取り組みが遅れている教科や、間違えた問題を優先的に出題するため、苦手が減っていきます。

③自動丸付け・解説と解きなおしシステム
問題を解くと、すぐに自動で丸付けされます。間違えた問題は解説を見てすぐに解きなおせるので、しっかり理解できます。


④アニメーション
紙の教材ではイメージすることが難しい立体の展開図の単元や理科の実験なども、自分で動かせるアニメーション教材で体感できるから理解が深まります。
子供の頃にこういうのがあれば展開図とかもっと理解できたかも!?

⑤反復学習
計算問題は、ベストタイムを意識して取り組むことで、早く正しく解く力が身につきます。文章題では、解くたびに違う問題に取り組めるので考えて解く力が身につきます。


⑥学習状況の確認
子供の学習状況をスマホやパソコンから確認することができます。


スマイルゼミのデメリット
タブレット学習には、上記のようなメリットがたくさんありますが、一方でデメリットもあります。
①英語
うちの子たちはECCで勉強させているので特に問題ではないのですが、正直なところ、1年生が最初から英語を一人で学習することは難しいのではないかなと感じます。
それでも3年生になるまでに英語に慣れておくためと考えれば有用です。
②丁寧に書かなくても認識される
多少字が適当だったり、汚くてもちゃんと認識してくれるせいで、タイムばかり気にして、丁寧に書かないくせがつく可能性があります。
タブレットの性能が良いのも良し悪しだね。
③子供に任せきりになってしまう
テキスト学習に比べて親が関わることが少ないので、子供がどんな問題を解いているのか、間違えた問題も解きなおしているけど、最終的にしっかりと理解できているのかがわからない場合があります。
たまには、学習内容を子供に教えてもらうとよいかもしれません。
スマイルゼミの受講料
スマイルゼミの受講料の支払い方法は、毎月払い、6か月分一括払い、12か月分一括払いの3つがあります。
小学1年生から6年生まで、学年問わず、
標準クラスでは、毎月払いに比べて、6か月分一括払いは月当たり500円(年間6,000円)、12か月分一括払いは月当たり900円(10,800円)安くなります。
発展クラスでは、毎月払いに比べて、6か月分一括払いは月当たり600円(年間7,200円)、12か月分一括払いは月当たり1,100円(13,200円)安くなります。
※会費の▶は新年度からの増額改定を表しています。


英語プレミアムを追加する場合でも、HOP、STEPコースは月680円、英検コースは月2,980円とお得です。(12か月一括払いの場合)

ほかに初期費用として専用タブレット代が9,980円かかります。
タブレット代はちょっと負担ですが、プログラミングや英語を含んだ教科数で、この受講料は家計にはかなり助かります。

なお、スマイルゼミでは自宅で気軽にタブレット学習を試せるようにと、タブレット返却で会費とタブレット代の全額返金を行っています。

【期間限定】受講料負担を軽減させる支払い方法
スマイルゼミの受講料を支払う際に、12か月分一括払いを選択して、その支払い用のカードとして、現在キャッシュレス決済普及や新年度会員獲得のために大型キャンペーンを行っているクレジットカードを設定する方法です。
たとえばこちらの三井住友カードは20%キャッシュバックが受けらるのでおすすめです。しかも現在はクレジットカード年会費が永年無料になっています。
三井住友カード
クレジットカード表面にカード番号や名前の記載のない新しいカードに生まれ変わったこともあり、現在入会すると、今だけ年会費永年無料で、利用金額の20%(最大12,000円)キャッシュバック中です。(2020年4月30日入会分まで)
60,000円支払ったら12,000円もキャッシュバックされるなんて嬉しいですね。

まとめ
我が家は兄妹で楽しく勉強しています。

一斉休校中は、学校の勉強が滞ってしまうので、これまでより多い、一日50~100問を目標に勉強させるつもりでいます。
家庭学習を検討されていた方は、せっかくだからこの機会に一度スマイルゼミを試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに我が家では、スマイルゼミや別に受講している進研ゼミ小学講座による家庭学習の成果を確認するために、継続して日能研の「学ぶチカラテスト」と四谷大塚の「全国統一小学生テスト」を受験しています。
こちらにその記事をまとめていますので、合わせてご覧いただけると幸いです。